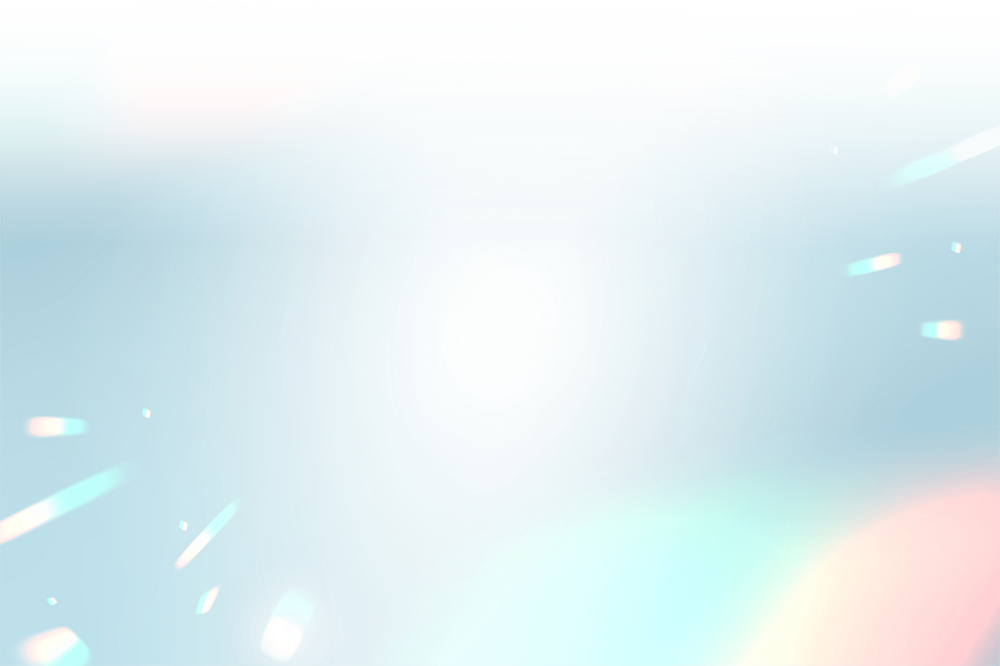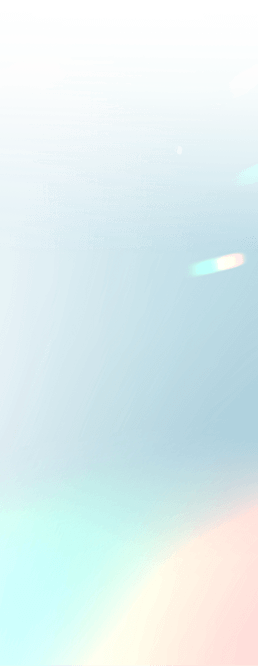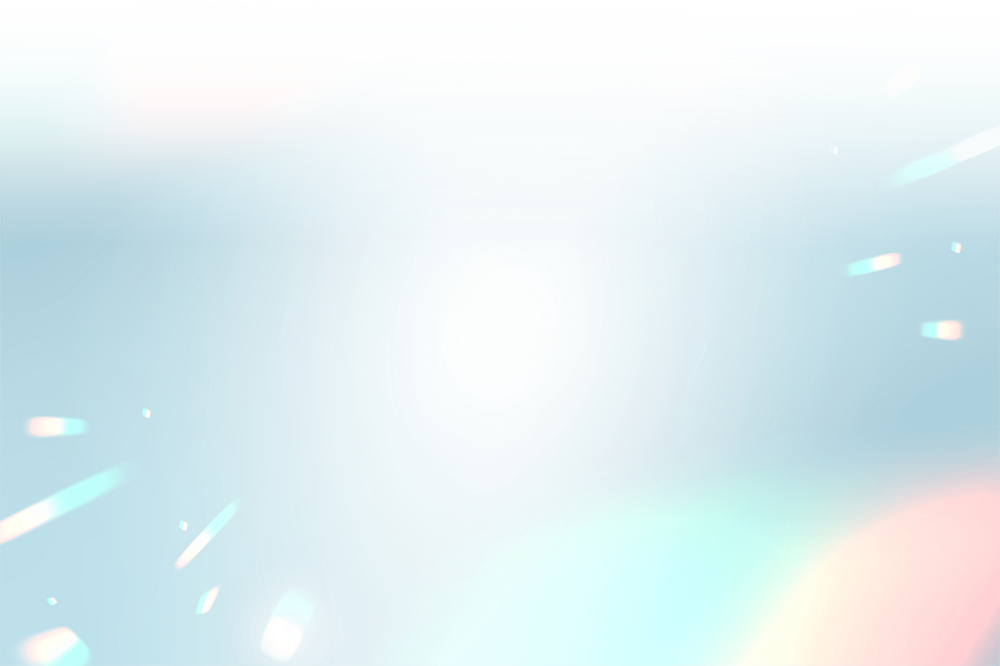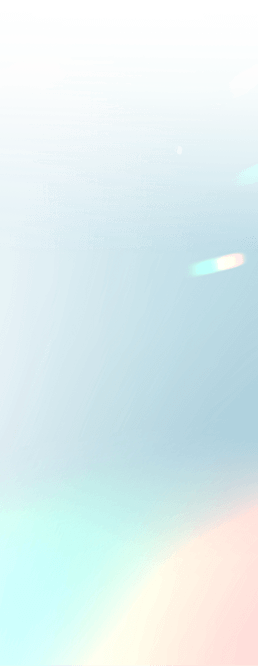うつ病や適応障害などのメンタルヘルス対策は近年大きな社会問題となっています。
特に獣医師は一般労働者よりも燃え尽き症候群や慢性的な疲労感を抱えやすいという報告もあり、獣医療業界におけるメンタルヘルス対策は、喫緊の課題といえます。
院長、勤務スタッフが「動物や誰かのために頑張る」その前に、自分自身の「心の健康づくり」のためのヒントとなれば幸いです。
小規模動物病院でも取り組める“働く人の心の健康づくり”
続けて、ICU看護師としての現場経験をもとに開業保健師として中小企業の健康管理・メンタルヘルス対策に特化したサービスを行なっている杉本 九実先生にお話を伺いました。獣医療の現場で求められる「心のケア」について、別業界の視点から考えます。
- Interviewee:株式会社PONO 代表取締役/帝京大学大学院公衆衛生学研究科 特任助教 杉本九実
- Interviewer:東京都獣医師会 広報委員会 委員長 伊藤優真
杉本九実先生のプロフィール
2008年に順天堂大学医療看護学部を卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院等を経て、2014年に株式会社PONOを設立。開業保健師として企業等の産業保健活動のコンサルタントや実務に従事。2024年に帝京大学大学院公衆衛生学研究科博士後期課程を修了し、公衆衛生学博士号を取得。猫ちゃん6匹と暮らす愛猫家。
健康づくりの体制が不十分な企業への支援とは?
- 伊藤
- まずは、現在のお仕事の内容について教えてください。
- 杉本
- 私は現在、株式会社PONOという会社を経営し、中小企業を中心に健康づくりの仕組みづくりや従業員の健康相談など、“働く人々の健康を守り支える”さまざまな支援を行っています。主な対象は、従業員数50名未満から1,000名程度の中小企業が多く、健康づくりの体制が不十分、もしくは推進したいという企業を支援しています。
- 伊藤
- そもそも、なぜこのお仕事を始められたのでしょうか?
- 杉本
- 私はもともとICU看護師でした。急性期の現場で働くなかで理想と現実のギャップに苦しみ、適応障害で3カ月の休職を経験しました。その後はなんとか現場復帰しましたが、バーンアウト(燃え尽き症候群)により看護師としての夢を諦めた経験があります。それをきっかけに、「これまでの経験を活かし、自分と同じような、働く現場で苦しむ人を支えたい」と強く思い、27歳で起業しました。
- 伊藤
- 動物病院の現場でも、杉本さんと似たようなケースが多いように思います。
- 杉本
- 本当にそう感じます。私自身、いざ現場に入ってみると想像以上に過酷でした。理想と現実のギャップに強く打ちのめされてしまう、という面では人医療も獣医療も同じであると感じます。
- 伊藤
- 獣医師も動物が好き、助けたいという強い思いでこの職に就いている分、そのギャップに悩む人は多いと思います。
- 杉本
- 特に学部生時代は、現場のキラキラした部分ばかりに目が行きがちですよね。自分が動物を救っている姿や、やりがいのある仕事に夢を持つことはとても大切なことです。でも実際には、命に関わる葛藤や職場の人間関係、長時間労働といった闇の部分と向き合わなくてはなりません。仕事をしてみないと分からないことは多いと感じます。
- 伊藤
- 現場に出て初めて知る苦しさというのは、多くの先生が経験しているかもしれませんね。
産業保健とは何か?
- 伊藤
- 話は戻りますが、産業保健について簡単にご説明いただけますか?
- 杉本
- 産業保健1とは、働く人々の心身の健康を保つための予防・保健活動全般を指します。法的には「労働安全衛生法」や「労働基準法」などに定められています。健康診断やメンタルヘルス対策、安全管理などを含む幅広い分野が対象となります
- 伊藤
- 事業場として最低限やらなければならないことはどのようなものがあるのでしょうか?
- 杉本
- 産業保健活動には法令で定められていることがいくつかあります。例えば、従業員数50 名以上の事業場における産業医の選任、健康診断やストレスチェックの実施、長時間労働の面接指導、などがあります。
しかし、従業員数50 名以下の小規模事業場などでは努力義務である事項が多く、産業保健活動やその体制が不十分であるケースが非常に多いです。
- 伊藤
- 動物病院では、院長が経営と診療の両方を担っているケースが多く、そこまで手が回っていない印象がありますね。
- 杉本
- 従業員に何らかの不調やトラブルが発生してから対策し始めるのでは遅いです。予防の観点からも、最低限必要とされる基本的な産業保健活動体制を整備することがまず大切です。

獣医療従事者は「自己犠牲型」が多い?
- 伊藤
- 僕自身も朝から晩まで働いているのが現状で、命に向き合う現場も多いのですが、獣医療従事者にバーンアウトを発症する人が多い点や自殺率が高いといわれる点について、どのような所感をお持ちですか?
- 杉本
- 今回、インタビューを受けるにあたりそのような現状を初めて知りましたが、とても衝撃的でした。産業保健分野としても取り組みを強化しなければならない喫緊の課題です。人医療でも獣医療でも、「命を守る」という行為の本質は同じです。そして、命と向き合うということは常に心を消耗するということでもあります。大学では「守るべき対象」のための知識は教わりますが、自分自身の守り方は誰も教えてくれないですよね。
- 伊藤
- 確かに、「自分は後回しにしても動物や飼い主のために」頑張ろうとする先生は多いです。
- 杉本
- 人医療や獣医療に関わる医療従事者に限らず、広く医療・福祉の世界で働く人は共感力が高く、真面目で責任感の強い人が多いと思われます。その特性ゆえに頑張りすぎてしまうのです。こうした人は自分を守ることやケアすることを後回しにして、知らず知らずに心身の負担を溜め込むことが多い傾向にあります。
それに加えてもう一つ大事な視点は、「感情労働」への理解です。命の現場では患者さんや飼い主さんとの関わりのなかで、自分の感情をコントロールし、相手に適切な感情表現を演じる場面がしばしばあります。怒り・悲しみ・不安などの感情を抑えることが多いため、精神的な負担が大きく、ストレスやメンタルヘルス不調を招きやすくなります。
- 伊藤
- 感情の抑制そのものが仕事の一部であり、大きな精神的負荷になるということですね。
- 杉本
- 「こんなことで辛くなるなんて、自分が弱いのではないか」と感じてしまう方も少なくありません。しかし自分を責めず、まずは自分の心や体を守る方法を知ることが大切です。
メンタルヘルス対策として、個人や職場で心がけたいこと
- 伊藤
- そのために個人や職場でできることは、どのようなことでしょうか?
- 杉本
- メンタルヘルス対策には「4つのケア」があります。まず1つ目は「セルフケア」です。自分自身のストレスに気づき、予防や対処をするためのケアのことです。2つ目は「ラインケア」です。これは管理職や院長といった立場の人がスタッフの変化に気づき、必要に応じて声をかけたり支援につなげたりするケアです。スタッフとのコミュニケーションを円滑にし、心の健康をサポートする役割を担います。この2つを意識するだけでも、職場の雰囲気は大きく変わっていきます。
また、見落とされがちですが管理職や院長といった、スタッフを支える立場の方にもセルフケアが必要です。ラインケアを担う人がセルフケアを後回しにした結果、ご自身が心身の不調をきたしてしまうケースも珍しくありません。
- 伊藤
- そうした立場の方が、自分自身を守るにはどうしたらよいのでしょうか?
- 杉本
- 一般企業であれば、管理職のさらに上の役職者が支援にあたることができますが、小規模の動物病院では上司という立場が存在しないことがほとんどです。その場合には、3つ目、4つ目のケアである「産業保健スタッフ等によるケア」や「事業場外資源によるケア」を活用することができます。私たちのような外部の産業保健専門職、地域や民間の支援機関がサポートするということです。
- 伊藤
- そのような支援があるのですね。働く人すべてに必要なセルフケアについて、何かコツがあれば教えていただきたいです。
- 杉本
- セルフケアとして私がおすすめしているのは、自分の心を守る手段を3 つ以上持つことです。例えば、サウナに行く、動画を見る、誰かと話す……何でも構いません。その手段が多いほど、ケアの幅が広がり心の健康を保ちやすくなります。
- 伊藤
- 気持ちをリセットできる方法を、あらかじめ複数確保しておくイメージですね。
- 杉本
- その通りです。そして、もう一つ大事なことは信頼できる相談相手を一人でもよいので持っておくことです。家族でも友人でも、獣医師仲間でも構いません。「何かあったときにはこの人に話してみよう」と思える存在がいることが、心の大きな支えになります。

復職者だけではなく職場全体のサポートがカギ
- 伊藤
- 例えばスタッフがメンタルヘルス不調で休職した場合、職場復帰時にはどのようなサポートが必要なのでしょうか?
- 杉本
- まず、復職者への接し方としては、普段どおりのコミュニケーションで大丈夫です。無理に気を遣い、腫れ物に触るような対応をしてしまうと、かえって双方が負担になってしまいます。一方で、業務の量や質については配慮が必要です。いきなり休職前の業務に戻すのではなく、まずは軽作業からスタートする、時短勤務や勤務日数を減らすなど、半年ほどかけて徐々に慣らしていく方が再発や離職を防ぎやすくなります。
私の場合、復職者とは月1回の面談を継続的に行い、変化を丁寧に見守ります。同時に、復職者の周囲で働くスタッフや上長にも個別面談を行い、困り事や悩みなどにアドバイスしています。
- 伊藤
- 単に職場復帰できればよいのではなく、職場にきちんと定着できるように周囲や専門職が協力して支えていくことが重要なのですね。
小規模動物病院でも活用できる外部の支援
- 伊藤
- 小規模動物病院では「外部の支援なんてうちには無理」と思ってしまいがちです。具体的に使える制度や窓口などがあれば教えていただけますか?
- 杉本
- ぜひ知っていただきたいのが「地域産業保健センター」2です。厚生労働省が設置している公的機関で、従業員数50名未満の小規模事業場が主な対象となっています。地域産業保健センターでは、労働安全衛生法で定められた長時間労働者や高ストレス者の面接指導、保健指導や健康相談などの産業保健サービスを提供しています。利用回数には制限がありますが、提供するサービスは無料です。
- 伊藤
- 無料で利用できるのですね。
- 杉本
- はい。まずは一度相談してみるのがおすすめです。また、弊社が提供しているような民間の産業保健サービスもあります。小規模事業場でも利用しやすい支援を提供しているところも増えているので、「うちみたいな規模じゃ無理」と諦めるのではなく、相談してみてほしいです。
ストレスチェックは労働者自身のセルフケアにつながる
- 伊藤
- 話は戻りますが、ストレスチェックについて詳しく教えていただきたいです。
- 杉本
- ストレスチェックの本来の目的は、事業主のためではなく「労働者本人が自身のストレス状態に気づき、セルフケアにつなげること」です。
- 伊藤
- 結果によって、労働者が不利益を被ることはないのでしょうか?
- 杉本
- ストレスチェックの個人結果は、本人の同意がない限り事業主には共有されないため安心して受けていただくことができます。高ストレス者は、本人が申し出をすれば産業医と面談することも可能です。
さらに大きな変化として、2025年5月に労働安全衛生法改正案が可決され、これまで努力義務であった従業員数50 名未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。2028年までに施行される見込みです。これにより、日本の全ての事業場が対象となるため、動物病院も例外ではありません。ストレスチェックは医師(産業医)や保健師などが実施者となり行われるため、われわれ保健師にとっても大きな転換期になるかと思います。
- 伊藤
- 動物病院でもこれがきっかけになり、早めに不調に気づいて対応できれば深刻化を防げそうですね。
- 杉本
- まさにそれが最大の目的です。私たちのような専門職が面談などを通してフォローすることで、「病院に行くほどではないけれど、ちょっとしんどいかも」という早期の段階でも支援ができることを期待しています。

働き方改革は、獣医療の現場にも必要ではないか
- 伊藤
- 今回のお話を通して、獣医療の現場でもメンタルヘルス対策の取り組みが重要であるとあらためて感じました。
- 杉本
- 今回のインタビューで感じたことなのですが、人医療の分野では、医師の働き方改革3が2024年4月から始まり、労働時間の上限が設定され、健康確保のための追加的措置が義務化されました。このように国をあげた改革が始まったものの、獣医師には適用されていません。命を対象とした仕事という意味では同じ職業なのに、獣医師だけが改革の外に置かれているという構造には違和感を覚えました。
- 伊藤
- 確かに、僕ら自身も「医療職」でありながら医師とは別枠で扱われていると感じることがあります。
- 杉本
- それこそがまさに、制度の狭間、もっといえば意識の狭間ですよね。まずは現場で働く先生方一人ひとりが、「自分たちは支援を受けてよい立場なのだ」と認識することが第一歩であると思います。
孤立させない仕組み作りが期待される
- 伊藤
- こうした考えを、業界全体に広げていくことが今後の課題ですね。
- 杉本
- まさにそうです。業界として、「困ったときには相談してよい」「外部支援を活用してよい」という文化や体制を整備していくこと、そして周知徹底することが、今後ますます重要になると感じています。
- 伊藤
- 東京都獣医師会としても、今回のお話をきっかけに、会員の先生方のメンタルヘルス対策をどう強化していけるか、あらためて考えていきたいと思います。
- 杉本
- この取材を通して、私自身も獣医療の現場が抱える課題や苦しみに気づかされました。医療職としての共通点も多く、支援の可能性は十分にあると感じています。個々の事業場にアプローチしていくことはもちろん大切なのですが、これからは、例えば獣医師会のような大きな機関と産業医や産業保健師が顧問のような形で協力体制を構築し、組織的にメンタルヘルス対策を推進することが大切になってくるのではないでしょうか。
※本記事はTOJUジャーナル7月号の特集内容から一部修正を行い、掲載しました。